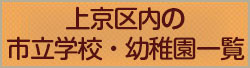地域に根ざし、京の暮らしの文化を支える銭湯「長者湯」
堀川上長者町を少し西に入った静かな住宅街。そこに、どっしりとした唐破風(からはふ)の屋根が目を引く銭湯「長者湯」があります。大きく「ゆ」と書かれたのれんをくぐり、下駄箱に靴を入れて中に入ると、番台から「いらっしゃい」と声をかけてくれます。100年以上にわたって地域とともに歩んできたこの銭湯には、どこか懐かしく、心がほぐれるような空気が流れています。今回は、三代目として40年以上銭湯を営まれている間嶋正明(まじままさあき)さんにお話を伺いました。

▲お話いただいた間嶋正明さん
長者湯の創業は1917年。当時は東堀川一条で銭湯を営んでいた初代が、現在の場所にあった銭湯を譲り受けて営業を始めました。1936年には現在のような唐破風の建物に改装され、その堂々とした姿は今も街並みに風格を与えています。
お湯は今もなお井戸水を汲み上げ、薪で沸かしています。重油やガスが主流となった今では珍しいこの方法も、自然の恵みに感謝しながら丁寧に湯を沸かす、長者湯ならではのこだわりです。

▲薪を割って火をくべます

▲京都は地下水が豊富だと実感する井戸。
梅雨時は水位がぐんと上がります
脱衣所に目をやると、そこには古くから大切に使われてきた品々が並びます。中でも、コリヤナギの枝で編まれた「柳行李(やなぎごうり)」は、奈良時代からある日本の伝統的な収納道具。着物文化の根付く京都では重宝され、長者湯でも修理を重ねながら大切に使い続けてきました。地元で職人がいなくなり困っていた際には、お客さんの紹介で兵庫県の職人と出会い、籠の新調が叶いました。そんなエピソードからも、銭湯を通じた人とのつながりが感じられます。

▲柳行李の籠。籠ごとロッカーにしまうのは、他府県ではあまり見られない、京都の銭湯に残る習慣だそう

▲1994年の改装時に描かれた冬の金閣寺(男湯)

春の清水寺(女湯)
タイルに釉薬(ゆうやく)で絵を描き焼いてあるのでいつまでも色褪せず現在に至っています

▲鯉が泳ぐ池に置かれた雪見灯籠
同じものが円山公園の池にもあります

▲1994年の改装時に設置した、近江八景を描いた透かし彫りの欄間

▲良質な井戸水を薪で沸かした湯
身体も心も温まりそう
間嶋さんは、もともと交通事故の査定をする仕事に就いていました。しかし「示談業務を通じて知る事故が悲しくて辛くて…」と振り返ります。結婚を機に家業を継ぎ、番台に立つと、「気持ち良かった」「あったまったわ-」とお客さんから直接声をかけられる日々に。「こんなに人に喜んでもらえる仕事は他にない」と、この仕事を“天職”と語ります。
間嶋さんは、地域との関わりを大事にしていたお父さんの姿に接していたため、自然と地域とのつながりができました。ご近所さんから「ソフトボールやらんか」と声がかかった時に、スポーツが好きな間嶋さんは二つ返事で加わり、やがて運営を担うようになって、今では聚楽学区体育振興会の会長を務めています。聚楽社会福祉協議会の副会長も務められ、様々な地域行事に携わる中で「敬老会、ご苦労さん」「あんたんところの風呂入ってるから元気や」と声をかけられることもあり、この地域で暮らしていることの喜びを感じるのだそうです。
2023年には、長者湯にとって大きな節目がありました。四代目として息子さんが家業を継ぐことを決め、それを機に大規模な改装を行ったのです。念願だったサウナの新設に加え、水風呂の拡張、カランや天窓の更新など、老若男女がより快適に過ごせる空間へと生まれ変わりました。
改装中には、銭湯同士の支え合いもありました。近くの「白山湯」が閉業の予定を延期し、長者湯の改装工事が終わるまで営業を続けてくれたのです。

▲地下水と同じ17-18度に保たれている水風呂

▲お客さんに好評のサウナ

▲「いつかは星空を眺められたら」と願う天窓
昭和の時代には京都市内に600軒あった銭湯も、経営者の高齢化や設備の老朽化、後継者が見つからないなどの理由によって、今では80軒ほどになりましたが、堀川西支部に所属する6軒は、LINEで情報を共有するなどして連携を保っています。
最近は、若い世代の利用も増えてきました。学生たちがグループで訪れ、お風呂で汗を流した後、脱衣所の一角にある休憩スペースでジュースを飲みながら談笑する様子は、まるで地域の憩いの場のよう。この場で出会ったアメリカンフットボール部の学生の試合を見に行ったこともあるそうです。
さらに、銭湯の前では無施肥無農薬栽培の野菜が並ぶ「軒先マルシェ」や干物やおかきが並ぶ「おつまみ屋」を開くなど、小さな交流イベントも行われています。オリジナルのお守りやTシャツなどのグッズを作ったり、京都府銭湯組合との協力で、毎月26日の「ふろの日」に、和束町のほうじ茶や美山のひのきの輪切りやかんな屑など地元の特産物を浮かべた風呂も用意するなど、様々な形でお客さんやご近所さんを楽しませる工夫をされています。
古いものを大切に、何よりも地域との絆をとても大切にしてきたその姿勢は、100年前から変わらず受け継がれてきたものであり、長者湯の魅力となっています。常連さんにとっては変わらぬ居場所として、観光客にとっては京都の暮らしと人情を感じられる場所として、多くの人の心を温めています。
今日もまた、長者湯には「いらっしゃい」とやさしく声をかける店主がいて、人の暮らしの中に、そっと寄り添うぬくもりがあります。肩までお湯に浸かりながら、身も心も温まる——そんな銭湯文化が、上京のまちで静かに、そして力強く息づいています。

▲2002年、京都市歴史的意匠建築物に指定されました
長者湯
営業時間:15:10-24:00(火曜日定休)
住所:京都市上京区上長者町通松屋町西入る須浜東町450
電話:075-441-1223
X: https://x.com/choujayu_kyoto
Instagram: https://www.instagram.com/choujayu.kyoto.sento/

カミングレポート
亀村佳都
まちづくり協働コーディネーター
「15時でもなく、15時半でもない。なぜ15時10分開店なのだろう」と尋ねてみると、開店前にお客さんが並んで待つ様子を見て、先代が15時半の開店を少しずつ早めたからなのだとか。「お父さんが生きていたら、今頃14時50分になってるんちゃうかな」と話す間嶋さんの、家族に対する愛、お客さんに対する愛を感じました。