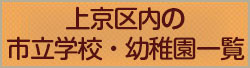西陣歴史の町協議会主催 再発見上京連続講座 交流で読み解く西陣―路地・歴史・文化―
西陣歴史の町協議会は、2012年から西陣地域の歴史や文化の研究、魅力あるまちづくりを目指して、地域の活性化と住民相互の交流を図る活動をしています。その活動の一環で、2024年10月12日(土)、京都市考古資料館を会場に「交流で読み解く西陣 ―路地・歴史・文化―」をテーマとする「再発見上京連続講座」が開催され、NPO法人 ANEWAL Gallery代表理事の飯髙克昌さんがお話をされました。会場には、若い世代からシニア世代の方まで幅広い世代が集まり、真剣な面持ちで講演に耳を傾けていました。

▲会場となった京都市考古資料館

▲西陣歴史の町協議会のみなさん
飯髙さんは、京都の大学で学び、建築設計事務所での仕事を経てフリーランスとして活動を始めた2004年に、西陣でANEWAL Gallery(以下、「アニュアルギャラリー」という。)を設立しました。家業の印刷・広告代理店にてアートディレクターを務めた4年間は活動から離れていましたが、再び京都に戻った2013年にアニュアルギャラリーをNPO法人化しました。

▲講師の飯髙さん
アニュアルギャラリーは、文化や芸術を活かし、人がまちの中で新しい視点や価値に出会う「外に出るギャラリー」をコンセプトにして、アートディレクターやアーティスト、学生を中心に運営されています。アートギャラリーの他、大判プリンターやレーザーカッターなどの機器を備えたものづくり工房、海外からのアーティストが創作活動をするための宿泊施設など5つの拠点が京都市内にあり、そのうち4つが西陣にあります。そのため、アニュアルギャラリーは西陣との縁が深く、約20年にわたって様々な活動を行ってきたことを、いくつか例を挙げて紹介されました。
1つめに事例として挙げられたのが、活動初期の2005年から現在まで続く「都ライト」です。町家のライトアップイベントで、外側から町家に光を照らすのではなく、町家の中に光を灯し、格子を通して外側に光を送ることによって日常の光景を非日常の空間へと昇華した斬新なものです。京都や大阪の大学に通う学生を中心とした実行委員会を立ち上げて準備し、上七軒や浄福寺通大黒町などの町家が並ぶ通りでイベントを行っています。当然ながら、町家の一軒一軒には住んでいる方がいらっしゃいます。地域の方々の協力なしには成り立たない「都ライト」のお話を伺うと、地域とのつながりを大切にしたいという思いが伝わってきました。
2つめの事例として、西陣歴史の町協議会メンバーに声をかけていただいたことがきっかけで、京都府庁でのアートイベント「ECHO TOUR(エコーツアー)」を行ったことも紹介されていました。2009年に始まったこのイベントは、2013年に「Musee Acta(ミュゼアクタ)」とタイトルを変えて従来よりも参加型の企画にし、毎年春の「観桜祭」、秋の「観芸祭」のイベントとして、来場者を楽しませています。
3つめに挙げられた海外のアーティストが京都に滞在しながら創作活動に取り組む「アーティスト・イン・レジデンス」事業では、ノルウェーから来たアーティストが西陣空襲について調査し、当時を知る地域の方にお話を聞き、まちを歩いて得たインスピレーションを作品にして、堀川商店街にあるギャラリーで展覧会を開いたそうです。
ほかにも、2019年に上京区140周年記念事業「上京OPEN WEEKS(オープンウィークス)」や「路地であそぼ」という子どもを中心としたイベントなど、西陣を中心に展開されたプロジェクトについてお話しされていました。

▲資料やスライドを用いた講演の様子

次に、それらの事業が生まれるアイデア出しから実現までの過程について教えていただきました。企画の目的の定め方や、アイデアを面白くするコツ、相手への伝え方など参考になるものばかりでした。
例えば、「町家を象徴的に表すイベント」というアイデアから生まれた都ライトでは、同様の事例があるか調べ、活動の社会的意義を考えたうえで、何のためにするのかと目的を決めました。それから「町家の中から光を出すのはどうか」「通りを彩るのはどうか」と学生たちとアイデアをひねり出し、「1軒でやってもインパクトがないのでエリア全体で試してみたらどうだろうか」と方向性を決めて取組の思いを地域の方々に伝えた結果、50軒の協力を得られたそうです。
そうして、今ではすっかり「都ライト」と名前が定着しています。「ネーミングも、企画を立てるうえで大事なポイントの一つと考えています」と伺うと、なるほど、これまで紹介いただいた「観桜祭」や「観芸祭」も、「上京OPEN WEEKS」や「路地であそぼ」も、コンセプトが決まり、人に伝わりやすい言葉を探した結果生まれたネーミングだということが分かりました。
西陣以外の例として、京北で、地下道を電車の車両に見立てて地元の子どもたちが絵を描くプロジェクトも挙げられました。「京北線の窓辺から」と名付けられたこのイベントは、「小学校前の道路が危ないので地下道を作ったものの、「暗くて怖いから」と通る人が少ない」との相談を受けて企画を考えることとなりました。地下道には、外部アーティストが描く一瞬注目される絵ではなく、地元の子どもたちが絵を描くことで、「子どもたちがたとえ京北を離れても、戻ってきた時に自分が描いた絵を見に来られるように」と地域とのつながりや未来を見据えたプロジェクトとなりました。
このように、地域とのつながりを考えたり、一度やってみた後の展開を考えながら持続性や発展性を考えたり、出てきたアイデアをどうしたら面白くなるかと考えたり、今までやったことのないような「チャレンジ」する部分はどこかと考えたりと、企画が実現するまでに大事にしているポイントを伝えられていました。
最後に、飯髙さんは、西陣に暮らし始めた頃の経験を伝え、人との関わりの大切さについてお話しされました。会社を辞めて独立した頃、家を探していた飯髙さんは、一軒の京町家とその大家さんに出会いました。お金もなく、大家さんに晩御飯をよくご馳走になっていた時、京都の季節の行事やマナー、町家の手入れの仕方などを教えてもらったそうです。初めのうちは「京都はいけず。どんないじわるを受けるんだろう」と構えていたこともありましたが、事務所を開放して地域の人と集まって、お酒を飲みながら話していると「みんな良い人たちだな」と西陣での暮らしは人との距離がほどよく近いと感じたそうです。
飯髙さんは、たくさんの方々にお世話になり、今があることを感謝されていました。人と交流して西陣の文化や魅力に気づき、アートやデザインの力でプロジェクトを行って地域社会に貢献しているアニュアルギャラリー。西陣のまちと人の魅力が一段と増す講座でした。
NPO法人アニュアルギャラリーの関連記事: https://www.kamigyo.net/public_html/person/dantai/20210311/

レポーター
渡辺優希
立命館大学法学部2回生
ただ頼まれたことをやるだけでなく、地域の方とのつながりや未来まで考えて活動されているのが伝わり、京都という地を大切に想っているのだと感じました。また、決まったプロセスだけでなく、よりよいものにしようと新たなアイデアも出されており、私も新たなイベントや拠点となっている町家に行ってみたいと思いました。
西形真次郎
立命館大学法学部2回生
イベント運営のお話の中で「ここで終わりません!」という言葉を何度も使っていらしたことが強く印象に残っています。ただイベントの企画・運営を行うのではなく、その後のことまで考えて注力する飯髙さんの活動はたいへん素敵だと思いました。
地域の方に心配されてしまうほどの献身性の裏には、過去に京都で受けた恩を地域に返したいという思いがあるかなと感じました。そんな感謝の輪がどんどん広まればいいなと思います。この記事が、その一助になっていれば幸いです。